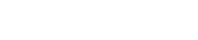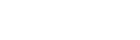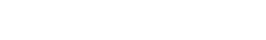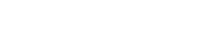1.低侵襲手術
ロボット支援下手術
ロボット支援手術は、「手術用ロボット」を使って行う先進的な方法です。お腹を大きく切り開く必要が少ないため、傷が小さく、痛みが少なく、回復が早いという利点があります。従来の腹腔鏡(ふくくうきょう)手術よりも、ロボットならではの多関節機能や手ぶれ防止機能、3次元映像による正確な操作が可能なため、より精密で安全な手術ができます。
当科では、食道がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなど、保険適応であるすべての手術にロボットを活用しています。日本内視鏡外科学会の内視鏡技術認定医や、ロボット支援手術プロクターに認定された医師を中心に低侵襲(体に優しい)手術を行っており、安全に適応を広げております。肝臓への転移がある大腸がんなど、複雑な症例でも1回の手術で同時に切除が可能になるなど、より進んだ治療を実現しています。今後もロボット手術は増え、消化器がん手術の中心的な方法になっていくと考えられます。



腹腔鏡・内視鏡合同手術 (LECS)
「LECS(レックス)」は、胃の粘膜下にできる腫瘍(GISTなど)に対し、胃カメラと腹腔鏡を同時に使って腫瘍を最小限の範囲で切除する手術です。これにより胃の機能をほとんど損なわず、体への負担が軽減できます。手術後の回復も早く、翌日から食事を再開し、5~7日で退院可能です。
また、同様の手技を十二指腸腫瘍に応用した「D-LECS(ディー・レックス)」も行っています。通常は困難な十二指腸腫瘍の内視鏡切除後、腹腔鏡で薄くなった壁を縫合・補強します。必要最小限の切除で、安全性と確実な治療を両立しています。

2.集学的治療
「集学的治療」とは、手術だけでなく、内視鏡、抗がん剤治療、放射線治療、そして免疫療法(免疫を活性化させてがんと戦う新しい治療)といった複数の方法を組み合わせることで、治癒率の向上を目指す治療戦略です。
手術が難しいと診断された進行がん(遠く離れた臓器へ転移があるステージIVのがん)に対して、抗がん剤や放射線などを組み合わせてがんを小さくし、その後に根治(治すこと)を目指す手術を行う方法を「Conversion Surgery(コンバージョン手術)」といいます(※「コンバージョン」とは「転換」の意味で、手術不能から手術可能へと状況を転換する治療法です)。従来であれば、余命数か月という非常に厳しい状態であっても、集学的治療を行うことで長期生存を目指すことができるようになりました。一方で、術後早期に再発をきたす症例もあり、慎重な手術適応の判断が必要です。

3.上部消化管
食道癌
食道癌には、手術、内視鏡治療、化学療法(抗がん剤)、放射線治療、そして免疫療法など、さまざまな治療法があります。これらの治療を組み合わせた集学的治療によって、病気を治したり、病気の進行を遅らせたりすることを目指します。当科では、2011年から内視鏡を用い小さな傷で行う低侵襲食道亜全摘術を始めました。内視鏡手術は、痛みが少なく、体への負担も軽いため、患者さんにとってメリットが多い治療法です。また、細かい血管や神経をしっかり確認しながら手術できるため、より繊細で質が高く出血の少ない手術が可能になります。また、2018年4月から食道癌に対するロボット支援手術が保険適応となり、当科でも2021年よりロボット支援下食道亜全摘術を導入しています。ロボット手術は、より細かな動きが可能で、手術後の合併症のリスク軽減が期待されています。


胃癌
胃癌は最大の原因であるピロリ菌の感染率低下、除菌治療の一般化などで減少傾向にあります。一方で患者さんの高齢化が進んでおり、当院においても胃切除のなかで75歳以上の患者さんの割合が40%近くを占め、年々増えてきています。このような状況では、安全性、根治性だけでなく患者さんの生活の質に配慮した治療の選択が重要です。体の負担を できるだけ軽くする治療(低侵襲)と胃の機能をできるだけ保つ治療(機能温存手術)を積極的に進めており、2023年には胃切除全体の92%を腹腔鏡とロボットを用いた低侵襲手術にて行っています。機能温存の点では、胃全摘が検討されることが多い、胃の上部や食道胃接合部癌に対し、できるだけ胃全摘を避け、胃の上部1/3の切除にとどめる手術(噴門側胃切除)を行っています。

GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor:ジスト)
GISTは、胃や腸の消化管壁の粘膜下にある間葉系細胞に由来する悪性腫瘍です。GISTは、とてもまれな腫瘍であり、その発症率は年間に10万人に対して1人から2人くらいとされています。GISTの治療の原則は、手術です。機能温存を目指してLECS(上述)を行い、根治性と低侵襲性の両立を目指しています。一方で、10cmを超えるような大きな腫瘍や周りの臓器へ広がりの程度により、すぐに手術を行わずに、手術前に薬物治療を行い(術前化学療法)、腫瘍を縮小させ手術を行うこともあります。再発あるいは遠隔転移があるGISTに対しては分子標的治療薬を用いた化学療法を行っています。当院では治療開始前に遺伝子変異検査を必ず行い、治療選択をしています。また、新薬の治験や臨床試験にも積極的に参加しており、様々な治療の選択肢をご提示できる環境を整えております。

4.下部消化管
ロボット同時切除
当科では、結腸がん、直腸がんに対して、ロボットを活用しています。肝臓への転移がある大腸がんなど、複雑な症例でも1回の手術で同時に切除が可能になるなど、より進んだ治療を実現しています。

細径鉗子
さらなる低侵襲化を目指して細径鉗子を用いたneedlescopic surgeryを取り入れています。これは、通常のポート配置で3mmの細径鉗子を用いる手術で、整容性の面で大きなメリットがあり、今後増えてくると思われる若年者のがん、あるいは若年者に多い炎症性腸疾患の手術等で有用です。

切除不能肝転移に対するconversion手術
大腸癌肝転移は、初診時に切除不能であっても、全身化学療法が著効して切除可能となるケースを多く経験しています。化学療法を適切なレジメン、タイミングで行いながら、肝臓外科医と連携して、時期を逸することなく外科治療に移行できるよう治療計画を立てています。

5.肝胆膵外科
肝臓・胆道・膵臓・脾臓の様々な疾患を対象に治療を行っています。肝胆膵領域の疾患は内科・外科共に専門性が高く、一般的な病院ではあまり扱わない分野の為、専門的な病院での治療が望ましいとされています。当院では消化器内科、画像診断・治療科、移植外科と毎週カンファレンスを行い、患者さんそれぞれのニーズに応じた最適な治療を提供できるように努めています。加えて癌の進行度や臓器機能および全身状態に応じて、ダメージの少ない治療を積極的に導入しています。
2023年に施行した肝胆膵領域の手術件数は382件であり、うち日本肝胆膵外科学会の高難度手術は合計175例とコンスタントに年間100例を越えています。2023年の肝切除数は158例(低侵襲手術103例)、膵切除数は108例(低侵襲手術68例)と、肝胆膵いずれの領域でも多くの手術を行い死亡例もありませんでした。肝胆膵外科学会高度技能専門医、内視鏡外科学会技術認定医による安全で質の高い手術と、肝臓学会指導医・胆道学会指導医・膵臓学会指導医による最先端の知識を生かした有効な治療法を提供できるように心がけております。

肝胆膵領域低侵襲手術
従来、肝胆膵外科領域は高難度な手術が多いため大開腹を余儀なくされることが多くありましたが、現在は手術技術と医療機器の進歩により急速に低侵襲手術(腹腔鏡下手術・ロボット支援下手術)が普及しています。低侵襲手術は開腹手術と比べ、傷が小さいことで術後の回復が早いだけでなく様々なメリットをもたらします。当科では日本内視鏡外科学会の内視鏡技術認定医や、肝臓・膵臓のロボット支援手術プロクターに認定された医師を中心に低侵襲手術を行っており、安全に適応を広げております。


ロボット支援下膵頭十二指腸切除術
2016年より良性から低悪性度腫瘍に対する腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術が保険収載され、当院でも2019年より本術式を積極的に導入し、現在までに90例を死亡例なく安全に行ってきました。現時点の熊本県内では熊本大学病院のみが施設基準をクリアしており、その経験をもとに2022年よりロボット支援下膵頭十二指腸切除術を導入し、これまで安全に適応を拡大しております。大きな侵襲を伴う従来の開腹手術は術後のQOLやADLの低下を招きやすく、術後の抗がん剤治療や再発時の治療が入りにくいケースもありました。ロボット支援下膵頭十二指腸切除術は、傷が小さく、腸への負担も少ないため術後の食事摂取が良好です。また、術後の早期回復だけではなく、膵臓手術特有の合併症である膵液漏も軽減できる可能性があります。現在までに44例に行い、死亡例なく術後在院日数も13日(中央値)と良好な成績です。


6.研究・臨床試験への積極的な参加と最新医療の提供
当科では、標準治療の確立や新しい治療法の開発を目的とした多施設共同臨床試験や治験に積極的に参加しています。これにより、最新の治療法を患者さんにお届けすることが可能です。日本国内だけではなく、世界的に行われている試験にも参加しています。また、試験によっては西日本では当科だけ参加している試験もあります。


7.患者さんへ直接お役に立てるがん研究の推進
消化器癌の診断は内視鏡やCTなどの画像検査で確認し、組織を採取して病理検査(顕微鏡検査)によって診断されます。肉眼で確認できないような微量な癌細胞を検出することができれば、手術の適応や転移・再発を予測し、患者さんのがんの状態によって適切な治療法を選択することができます(個別化医療)。しかし、そのような微量な癌細胞を検出するシステムは診療に応用されていません。そこで、当科では、熊本大学工学部の先生方と地元企業の方々と微量な癌細胞を検出するフィルターの製作を行ってきました。小型、安価、簡便に測定することを目指して開発しました。現在は臨床試験として、実際の消化器癌の患者さんの血液中のがん細胞の検出を行っています。実験的には1ml中の血液から癌細胞を検出することが可能です。全国規模の製作チームとなり、複数の特許を取得し、いよいよ製品化の段階まで来ています。


〈この記事は2025年1月1日時点の情報です〉
- 病院について
-
- 病院長あいさつ
- 基本理念・患者さんの権利と責務
- 沿革概要
- 組織図
- 役付職員
- 職員数
- 病床数
- 診療科別延べ患者数
- 地域別外来・入院患者数
- 予算
- 臨床検査数
- 手術及び麻酔件数
- 画像診断及び放射線治療件数
- 出産児数
- 処方枚数・件数・剤数
- 病理解剖件数
- 血液製剤使用数
- 末梢血幹細胞採取件数
- 医療機関の開設・承認等
- 施設基準届出状況
- 先進医療A・B
- 医療機関の指定等
- 学会認定
- 医療安全管理体制
- 施設
- 基幹・環境整備(屋外環境整備等)
- 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「施設基準」に係る掲示事項
- 病院機能評価の認定について
- 企業等からの資金提供状況
- 病院機能指標について
- 医療安全管理の通報窓口
- 病院情報の公表
- 病院アドバイザリー会議
- 病院監査委員会
- 臨床研究に関すること
- 臨床倫理コンサルテーション
- 医師の働き方改革について
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する情報公開について
- 患者満足度調査
- ご意見について
- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針
- ダイバーシティ推進について
- 院内保育所について
- 病児保育室「Mimi」について
- ネーミングライツパートナー募集
- 子どもの患者さんの権利と約束
- 大学病院改革プラン
- 広報誌・冊子
- 動画コンテンツ
- ソーシャルメディアガイドライン